成瀬整骨院ブログ
腰椎穿刺・髄液採取法の手技について 2/2
2014年5月14日 12:21
こんにちは横浜市金沢区の変形性膝関節症・成瀬整骨院のスタッフです。腰椎穿刺・髄液採取法の手技について以下参考として引用します。2/2
今日の治療方針
私はこう治療している
総編集 山口 敬 北原光夫 福井次矢
TODAY'S THERAPY 2010 医学書院より引用
腰椎穿刺・髄液採取法
Lumbar puncture(spinal tap)and cerebrospinal fluid collection
金子直之 東京医科大学准教授・救急医学
4.穿刺 腰椎穿刺針のカット面を頭側に向けて、棘突起間で背中の面に垂直、または少し頭側に向けて穿刺する。針の方向は成否にかかわるので、刺入の途中でも繰り返し確認するほうがよい。骨に当たる抵抗があれば方向を少しずつ頭側に変える。硬膜を貫いたら内針を抜き、髄液の流出を確認する。髄液が血液の場合は、真の血性髄液かいわゆるtrauatic tapかの鑑別が必要になるが、後者の場合はしばらく流出させるとすぐに淡くなるので、その場合は透明になるのを待って採取する。髄液流出がなければ内針を入れてさらに数mm刺入してみるか、針を回転させながらゆっくり抜いてみる。それでも流出がなければ針を抜いて再度穿刺する。硬膜までの距離は新生児で1-2cm、幼児で3cm、年長児以上で4-6cmである。
5.髄液圧測定 外筒に三方活栓を付け、圧測定棒を接続して初圧を測る。髄液上昇が止まり呼吸性に上下する中央値を髄液圧とする(正常60-150mmH2O)。200mmH2Oを超える場合は頭蓋内圧亢進と考え、検査を中止する。
6.Quecknestedt試験 くも膜下腔の開通性を検査する試験で、両側頭静脈を10秒間圧迫すると圧が100mmH2O以上上昇し、圧迫解除後10秒以内で元に戻るのが正常である。
7.髄液採取と減圧測定 採取は自然流出にまかせ、それを試験管で受ける。採取量は最小限にとどめる。採取後は終圧を測定してから針を抜いて消毒し、絆創膏を貼付する。
8.穿刺後の注意 穿刺後の頭痛を軽減させるため、1時間程度の安静臥位をとらせることが好ましいが、エビデンスはない。対麻痺などの神経症状の有無を確認する。
交通事故サイト:横浜市金沢区のむち打ち治療なら成瀬整骨院
携帯サイト版:横浜市金沢区の変形性膝関節症なら成瀬整骨院
電話045-785-5976(完全電話予約制)
横浜市金沢区寺前1-5-17
京浜急行金沢文庫駅東口徒歩8分
駐車場3台完備

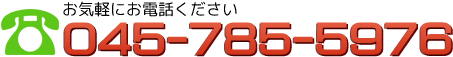


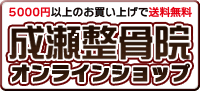
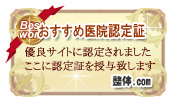
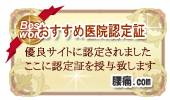
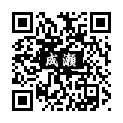
■コメントする